【中学生】理科の計算問題が苦手な人
理科の計算問題が苦手な人
中学で学習する理科では、計算問題が出てくる単元があり、苦手な人が結構いると思います。数学ができないから理科の計算問題もできないと思っているかもしれませんが、どちらかというと、その前の算数がきちんと理解できていないのではないでしょうか。計算問題が出てくる主な単元は、水溶液と濃度、物質の密度、力のはたらきと圧力、電流とその利用、仕事と仕事率、運動とエネルギーなどですが、割合や速さなど、いずれも算数で習ったような内容が多く含まれています。
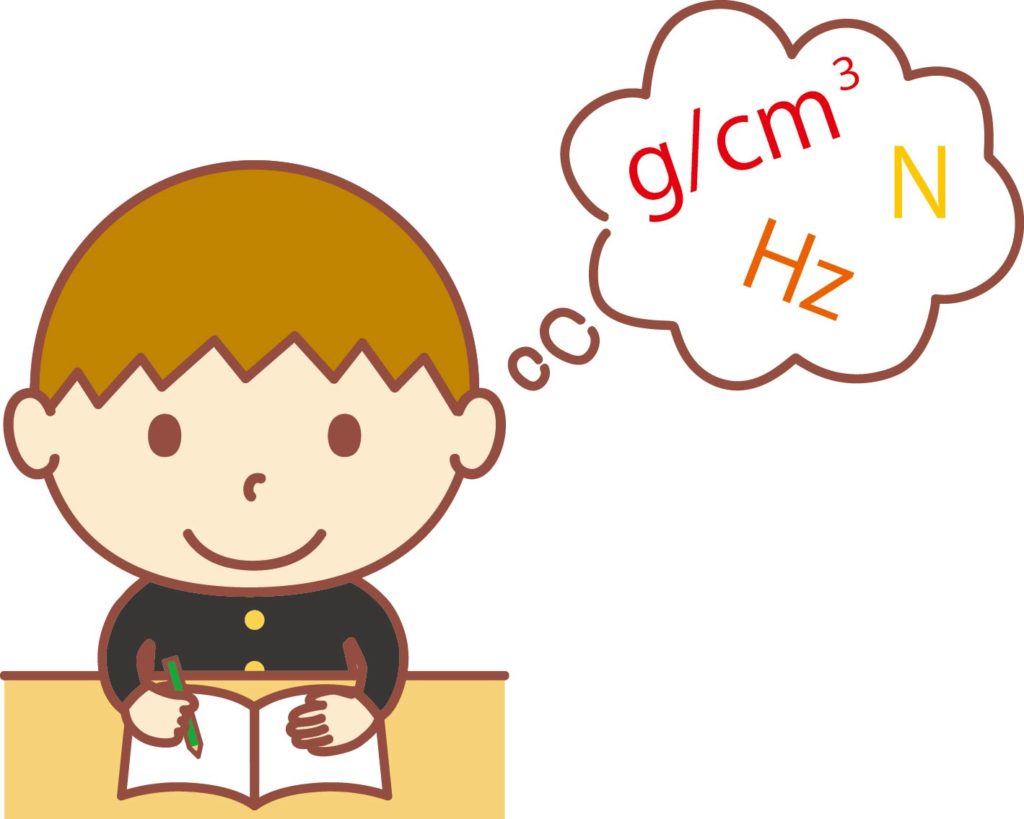
理科に必要なのは算数の力
例えば中学理科の化学分野で習う、水溶液の質量パーセント濃度ですが、これは名前の通り濃度の割合(パーセント)を求める問題がでてきます。しかしこの問題は、小学5年生の算数で出てくる食塩水の問題とほとんど同じです。小学校では食塩水の”こさ”という呼び方をしますが、理科では、質量や濃度といった言葉を学んだうえで、同じような計算をしているだけなのです。また、密度や圧力は、算数で学習した単位量あたりの大きさと同じ考えで計算することができ、力のはたらきは算数の比例、運動は算数の速さなどが理解できていれば、同じように解くことができます。しかし、算数の割合や速さといった単元は、小学生がよくつまずく単元でもあります。きちんと理解できておらず、なんとなくできた状態でやり過ごしてきた人は、苦労するかもしれません。
単位を意識する
理科の計算問題が苦手という人は、重さや距離などの単位を意識していない人が多いように思えます。例えば「1Vの電圧で100mAの電流が流れたときの電力を求めなさい。」という問題で、電力は電圧×電流だから、1×100=100Wだと計算する生徒をしばしば見かけます。しかし、電力を計算するときは、mA(ミリアンペア)ではなく、A(アンペア)という単位を使わなければならないので、正しくは1×0.1=0.1Wです。理科の計算問題でよく間違える生徒の中には、そういった単位を気にせず、ただ問題文の数を使って式を書いている人を見かけます。数学の問題にも言えることですが、単位を意識して問題を解くことは大切です。
理科は情報を読み取る力も重要
理科は、問題に実験の説明であったり、状況や条件などの情報が書かれていることがよくあります。そのため、問題文をしっかり読むことも求められます。単位を読み取ることも、その一部と言えるでしょう。また、グラフや表もよく出てくるので、その中から必要な情報を得る必要もあります。近年は英語など他の教科でも、情報の取捨選択を求める問題が増えてきましたが、理科は以前からそういった問題が多く出題されます。こういった問題が苦手な人は、学校の授業だけではなかなかできるようにならないため、できるだけ問題をたくさん解いて、慣れる必要があります。
算数の理解は重要
繰り返しになりますが、小学校で学習する算数は中学校の理科の土台となります。もちろん中学校の数学にも直結するので、算数がいかに重要な科目であるかが再認識させられます。ただ、形だけおぼえて算数の問題を解くだけではいけません。例えば「速さ=道のり÷時間」だけ暗記するのではなく、「時速は1時間に進む道のり」「分速は1分間に進む道のり」であるなど、その本質を知る、内容をしっかり理解することが何より重要です。